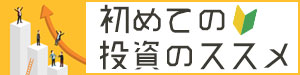中小企業の経営者なら、節税対策について気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は中小企業の経営者向けに、法人ができる節税対策を5つ紹介します!
法人がやっておきたい5つの節税対策
①青色申告で特別控除を受ける
法人の経営者であれば、節税の基本としてやっておきたいのが確定申告の方法の1つである青色申告です。
なぜなら、青色申告は税制面でかなり優遇されるからです。
青色申告を利用するメリットは以下の通りです。
<法人が青色申告を利用する主なメリット>
|
(1)赤字を10年間繰り越せる (2)赤字を前年の黒字と相殺して税金の還付を受けられる (3)申告税額の誤りがあった時に、税務署に異議申し立てできる (4)30万円以下の固定資産の取得原価を全額償却できる (5)”推計課税”の対象外になる |
(1)の「赤字を10年間繰り越せる」とは、法人がある事業年度で税務上の赤字を出した時に、その赤字額を10年間に渡って控除できる仕組みです。
例えば、以下のような売上を想定します。
前期:500万円の赤字
当期:400万円の黒字
当期では400万円の黒字でしたが、前期では税務上500万円の赤字が出るため、当期の課税所得は0円にあります。つまり、当期の課税所得が前期の赤字で賄われるため、当期は法人税を納付する必要がなくなります。
(1)と似たような制度に、(2)の「赤字を前年の黒字と相殺して税金の還付を受けられる」があります。当期で赤字が出た場合は、前期の黒字から赤字分を差し引くことで、前期で支払わなくてもよくなった法人税額が還付されます。
例えば、以下ような場合を考えます。
前期:1,000万円の黒字、300万円の法人税を支払う
当期:2,000万円の赤字
この場合、当期の赤字分を前期に繰り戻せるので、前期の課税所得が0円になります。そのため、前期の300万円の法人税は還付されることになります。
(4)では青色申告の特典として、中小企業等が30万円以下までの少額減価償却資産を取得した場合、その取得価額を損金に算入することができます。
少額減価償却資産取得価額の損金算入の概要は以下の通りです。
<中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例>
|
対象者 |
①と②に該当する中小企業、または農業協同組合 ①資本金が1億円以下 ②雇用する従業員が常時1,000名以下 |
|
取得価額を減価償却できる条件 |
①と②の両方を満たすこと。 ①取得価額が30万円未満の少額減価償却資産 ②2006年4月1日~2020年3月31日までに資産を取得するなどして事業用に使用し始めた場合 |
|
備考 |
事業年度で少額減価償却資産の合計額が300万円を超える時は、300万円までの取得価額が限度額になる。 |
上の図から分かるように、青色申告では30万円の少額資産でも損金にできるので、その分課税所得を減らすことが可能になります。
(5)の「推計課税」は青色申告の法人にして適用することはできません。
推計課税とは、税額計算の根拠がない時に「あなたは支払う税金はこれぐらいですね」と税務署側が決める方式です。
主に白色申告の法人に対して行われ、資料がない以上法人は異議申し立てをすることはできません。ただし、青色申告の法人でも税額計算が悪質だと税務署が認めた場合には、青色申告が剥奪され推計課税になることもあります。
上記の他にも青色申告のメリットはたくさんあります。それに対して、青色申告による手間やデメリットはほとんどありません。特に理由がなければ、青色申告を利用するのが賢明です。
青色申告を受ける場合には、法人設立から3ヵ月以内に所轄の税務署へ届出を行う必要があります。会社設立から事業年度終了日まで3ヵ月もない時は、その事業年度終了日までが届出期限です。
②役員に給与を支払って節税する
法人の節税対策で有名な方法として、役員報酬を損金にして節税する方法があります。
たしかに、役員報酬は大きな節税効果を見込めますが、単純に役員報酬がそのまま損金になるということではありません。
役員報酬を損金にするためには、下の3つのいずれかに該当する必要があります。
<役員報酬を損金に算入する条件>
|
(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)業績連動給与 |
(1)の「定額同額給与」とは、毎月の給与が同額の場合に、役員報酬を損金に算入できます。
例えば、ある会社の役員の年間の役員報酬が1,200万円とします。
この時、役員が毎月100万円ずつ同額で役員報酬を受け取れば定期同額給与に該当します。逆に「ある月は多めの200万円で、ある月は50万円で少なめにしよう!」では定期同額給与にならないので、注意してください。
役員報酬金額の改定は、事業開始年度から3ヵ月以内に限り可能です。株式会社の場合は、株主総会や取締役会を経て金額が決まります。
とはいえ、定期同額給与で役員報酬が毎月同額でも、ある時期に急にお金が欲しいというケースもあります。そんな時に役立つのが(2)の「事前確定届出給与」です。
「マイホームを買いたい!」
「仕事頑張ってるご褒美に、高い車を買いたい!」
このような急な出費に対応するために、事前確定届出給与を使います。
「事前確定届出給与に関する届出書」を前もって税務署に届け出ることで、役員報酬が定額でなくても損金にすることが可能です。事前確定届出給与では、事前に支払時期と支払金額を決めておきます。
ただし、事前確定届出給与を利用するには、以下のいずれか早い日までに届出をする必要があります。
|
A 株主総会等で役員報酬に関する決議をした日から1ヵ月後 B 会計期間開始の4ヶ月後 ※(新たに法人を設立した場合)法人設立から2ヶ月後 |
例えば、
事業開始日:2020年4月1日
株主総会:2020年6月1日
この場合は、Aは「2020年7月1日」なり、Bは「2020年8月1日」になります。Bの方が早いので、2020年7月1日が税務署への届出期限になります。
要するに、「急に車欲しくなったし、来月の役員報酬を500万増やそう!」としてしまったら、定期同額給与にも該当しなくなり役員報酬が損金になりません。役員報酬を損金にするには、前もって計画を立てる必要があります。
③太陽光発電の設置で節税する
実は、中小企業は太陽光発電設備の導入で節税することができます。
まず、太陽光発電設備は有形固定資産に該当するので、資産計上し減価償却が可能になります。太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。
国税庁HPによると、太陽光発電設備は自家用発電設備であることから「機械及び装置」と扱われます。したがってその耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」の「主として金属製のもの」に該当し、法定耐用年数は17年になります。
減価償却分は経費として計上できるため、その結果、所得額が減り、納税額も少なくなります。
また、太陽光発電設備の設置は「中小企業経営強化税制」の対象になります。
2017年4月1日~2021年3月31日の間で青色申告を受けた中小企業が太陽光設備を購入して使用開始した場合、「特別償却」か「税額控除」のどちらかを受けることが可能です。
ここで言う中小企業とは、資本金が1億円以下で従業員数が常に1,000名以下の法人のことを指します(ただし、その事業年度開始日前3年以内の各年の平均所得が15億円を超える場合は対象外)。
<中小企業が太陽光設備取得で可能な節税>
下のどちらか一方を選ぶことになります。
|
(1)普通償却限度額に加えて、取得価額の全額を即時償却する (2)太陽光発電設備の取得価額の内7%相当額を税額控除する(さらに、資本金3,000万円以下の場合は取得価額の10%) |
(1)の特別償却を選ぶと、通常の減価償却費に加えて、取得価額の全額を太陽光発電設備を購入した事業年度に即時償却することが可能です。
(2) では、太陽光発電設備の取得価額の7%を税額控除できます。税額控除は所得控除とは違い、課税所得から計算した法人税より直接控除されるので、節税効果が大きくなります。さらに、資本金3,000万円以下の場合は、取得価額の10%の税額控除が可能です。
例えば、資本金5,000万円(従業員500名)の中小企業が太陽光発電設備を1,000万円で取得すると、その事業年度の法人税70万円が税額控除されます。
また、その事業年度の法人税の20%が税額控除の限度額になるため、太陽光発電を取得した事業年度中に全額控除できないことがあります。その場合は、限度超過額を1年間繰り越すことが可能です。
長い目で見れば、(2)の税額控除の方が直接法人税から差し引けるので、税制面でお得なことが多いです。ただし会社によって変わってきますので、詳しくは税理士に相談してください。
④交際費を5,000円以下にして損金に算入する
資本金1億円以下の法人の場合、接待などに関わる5,000円以内の飲食費は損金に算入できます。正確には、飲食代の合計額を参加人数で割った時に1人当たりが5,000円以下になれば大丈夫です。
例えば、飲食代の合計額が2万円でも、5人参加すれば1人当たり4,000円になるので、損金算入の条件を満たします。
ただし、1人当たり5,000円以下の交際費を損金に算入するためには、以下の全てを記載した書類を保存していることが条件です。
<1人当たり5,000円以下の飲食代を損金にする条件>
(1)~(5)を全て書類に記載するなどして保存する。
|
(1)飲食をした年月日 (2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3)飲食をした人数 (4)飲食代、及び飲食したお店の名前、所在地 (5)その他参考となるべき事項 |
※国税庁HP「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」より
飲食代の領収書の裏面でも構わないので、上の必要事項を必ずメモしておくようにしましょう。
さらに、資本金1億円以下の中小企業は年800万円までの交際費を無条件で損金に算入することができます。こちらは「5,000円以下の飲食代」のような条件はなく、交際費が年間800万円になるまで損金に算入できます(ただし、社外取引先を含まない社内の飲み会や慰安旅行などは交際費に含まれません)。
⑤小規模企業共済で掛金を所得控除する
中小企業の経営者におすすめしたいのが、「小規模企業共済」による役員の所得控除です。
小規模企業共済とは、中小企業の役員などが廃業後や退職後の退職金などを積み立てる制度で、掛金が全額所得控除になるメリットがあります。さらに、役員報酬に掛金を加えることで、実質的に掛金を損金に算入することも可能です。
小規模企業共済は国が小規模の経営者や個人事業主向けに行っている制度ですので、安心して利用できます。
小規模企業共済の概要は、以下の通りです。
<小規模企業共済の概要>
|
制度の名称 |
小規模企業共済 |
|
運営主体 |
中小機構(独立法人 中小企業基盤整備機構) |
|
制度の目的 |
小規模企業の経営者や個人事業主が、廃業・退職後の資金の積み立てのため |
|
節税対策 |
掛金が全額所得控除になる |
|
加入条件 |
・建設業、運送業、不動産業など→雇用する従業員が20名以下 ・卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)→雇用する従業員が5名以下 など |
|
掛金 |
1,000円~70,000円の間で、500円単位で自由に決められる。加入後に金額の変更可。 |
|
共済金の受け取り |
①一括②分割③一括と分割の併用 |
役員が現役期間中に支払った掛金は、役員の課税所得から全額所得控除されます。課税所得が減るので、その分役員の所得税が減るということですね。
また、役員退任時の受取は、「退職所得扱い」または「雑所得扱い」になります。
受け取る共済金の扱いの違いは以下の通りです。
|
一括で受け取る→「退職所得」の扱い 分割の受け取る→「公的年金等の雑所得」の扱い |
例えば、退職所得控除であれば、以下のように計算されます。
『退職所得の計算方法』
「(収入金額※ - 退職所得控除額) × 1/2 = 課税退職所得」
※源泉徴収前の収入
<退職所得控除額の計算方法>
|
勤続年数 |
退職所得控除 |
|
20年以下 |
40万円 × (勤続年数)※80万円未満の場合は、80万円 |
|
20年超え |
800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
※国税庁HP「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」より作成
(画像引用:国税庁HP「退職金と税」)
上の図から分かるように、課税退職所得に対して所得税が計算されます。そのため、共済金で受け取ると控除などが受けられ、その分節税が可能になります。
一方の「公的年金等の雑所得」も同様に、直接所得を受け取るよりも税金の支払額が少なくなります。
小規模企業の役員が小規模企業共済を利用すると、役員の退任後の退職金額を積み立てながら、同時に節税もできるかなりお得な節税対策になっています。
法人がやってはいけない2つの節税対策
最後に、法人がやってはいけない節税方法を2つ紹介します。
よく中小企業の経営者が勘違いしがちな内容も含まれるので、ぜひ参考にして下さい。
①節税の為に必要ない物を買う
一番勘違いしがちな法人の節税対策が、節税のためにわざと必要のない物を買うことです。
利益を残さないようにわざと高い物を購入する会社もありますが、それでは資金繰りが悪くなるだけです。
例えば、以下のような場合を考えてみましょう。
〇A社、B社ともに税引前当期純利益が1,000万円
〇法人にかかる税率が30%
<A社>
|
A社の税引前当期純利益 |
1,000万円 |
|
A社の税金納付額 |
300万円 |
|
A社の税引後当期純利益 |
700万円 |
<B社>
B社は節税対策のために、決算前に今必要のない資材などを200万円分購入する。
|
B社の税引前当期純利益 |
800万円 (1,000万円-200万円) |
|
B社の税金納付額 |
240万円 |
|
B社の税引後当期純利益 |
560万円 |
B社の方が課税所得が少ないので60万円の節税ができますが、当期の内部留保額がA社より140万円少なくなっています。結果、必要のない資材などを購入した挙句、80万円の利益を失ったとも言えます。
節税そのものを節税対策の目的にしてはいけません。節税の本当の目的は、会社が一生懸命稼いだお金をできるだけ多く手元に残すことです。
また、会社の内部留保が少ないと、金融機関からの融資が受けづらくなります。金融機関は、きちんと利益を出して税金を国に納めている会社を評価します。
利益を圧縮して資金繰りを悪くするぐらいなら、経費を節約して従業員への給料を増やす方がよっぽど会社のためになります。
②資本金は1億円以内の方が節税しやすい
資本金は1億円以下の方が、税制面で優遇されることが多いです。
資本金が1億円以下によるメリットは、以下の通りです。
<資本金が1億円以下によるメリット>
|
①欠損金の繰越ができる ②欠損金の繰戻ができる ③800万円までの交際費を損金に算入できる ④30万円までの少額減価償却資産を損金に算入できる ⑥太陽光発電設備の購入で特別償却か税額控除を受けられる(2021/3/31まで) ⑦法人税率が安くなる ⑧外形標準課税の適用から外れる |
このうち、①~⑥はこの記事で紹介してきた内容です。これらのお得な節税対策は、資本金が1億円以下になることによって大きな効果を発揮します。
⑦では、資本金1億円以下の法人は、資本金1億円越えの会社よりも法人税率が安くなります。
以下の図は、資本金が1億円以下と1億円越えの会社でそれぞれの法人税率を比較した表です。
<資本金毎の法人税率比較表>
|
所得の区分(平成31年4月1日以降) |
||
|
年800万円以下の部分 |
年800万越えの部分 |
|
|
資本金が1億円以下 |
15% (適用事業者は19%) |
23.2% |
|
資本金が1億円以上 |
23.2% |
|
このように、資本金が1億円以下の法人は、年800万円を下回る課税売上は15%になり、一方のの23.2%に比べて法人税率が低くなります(ただし、適用事業者※は19%)。
※適用事業者とは、事業年度開始日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人のこと。
⑧の外形標準課税とは、赤字の会社にも法人事業税を課すために、所得だけでなく事業所の面積や報酬等を考慮して税金を計算する課税方式です。ただし、外形標準課税も資本金1億円以下の中小企業は対象外になります。
以上のように、資本金を1億円以下にすることで税制面で優遇されることが多いです。資本金が1億円を超える場合は、減資を検討するのも1つの手です。
まとめ
中小企業向けの節税対策として、取り組みやすいものから5つ取り上げました。
この記事の中で気になる節税対策があったら、ぜひ税理士と相談しながら取り組んでみてください!
関連する記事
この記事が気に入ったらいいね!しよう
マネストの最新エントリーが見られます。
Twitterでマネストをフォローしよう! @ManeSto_comさんをフォロー