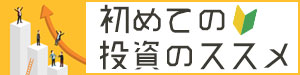「業務用に車を買おうと思っているけど、減価償却についてよくわからない…」
このような疑問にお答えするために、車の購入を検討している法人や個人事業主に向けて、車の耐用年数や減価償却費の計算方法について詳しく解説します。
本記事では計算方法の例や表を使って説明するので、減価償却についてよくわからない方でも理解しやすくなっています。
そもそも減価償却とは
減価償却とはなんのことでしょうか?
減価償却とは、建物や機械装置、車両運搬具など、1年以上使う資産(固定資産)の取得費用を何年かに渡って経費に計上することをいいます。
固定資産は時間が経つにつれて劣化するので、資産価値が目減りします。そのため、固定資産の取得年度に一括で経費に計上してしまうと、固定資産の使用期間中は経費として計上することができません。
そこで減価償却は、適正に経費計上することを目的として、資産ごとにそれぞれ決められた期間(耐用年数)に分けて減価償却費を計上します。
減価償却の対象になる資産は「1年以上使う10万円以上の資産」です。ほとんどすべての車の価格は10万円以上で、1年以上使うと思いますので車は償却資産の対象になります。
まずは車の耐用年数を知る
車を減価償却するにあたって、まずは車の「耐用年数」を知っておきましょう。
耐用年数とは、固定資産を減価償却できる年数のことをいいます。実は、車の耐用年数は「車の種類」で変わります。
そこで、車ごとの耐用年数について見ていきましょう。
①一般自動車の場合
一般的な事業者が車を所有する場合、耐用年数は普通車が6年、軽自動車が4年です。
<一般的な事業者が保有する車の耐用年数>
|
自動車 |
耐用年数 |
|
普通車 |
6年 |
|
軽自動車 |
4年 |
|
貨物自動車(ダンプ式) |
4年 |
|
貨物自動車(ダンプ式以外) |
5年 |
|
報道通信用の車(テレビ中継車など) |
5年 |
※東京都主税局「減価償却資産の耐用年数表」より作成
普通車の耐用年数は6年と、車の中で最も長くなっています。
②運送事業者、貸自動車、自動車教習所の場合
タクシーやバスなどの運送事業者や、レンタカーなどの貸自動車事業、自動車教習所の場合、さきほどの一般用とは耐用年数が変わります。
<運送事業者・貸自動車・自動車教習所の耐用年数>
|
自動車 |
耐用年数 |
|
普通車(乗合自動車を除く) |
4年 |
|
乗合自動車 |
5年 |
|
小型車(積載量または総排気量が2リットル以下) |
3年 |
|
大型乗用車(総排気量が3リットル以上) |
5年 |
|
被けん引車(トレーラーなど) |
4年 |
※東京都主税局「減価償却資産の耐用年数表」より作成
このように運送事業者が使う車の耐用年数は、種類によって細かく決められています。
③中古車の場合
中古車の場合、新車とは耐用年数の考え方が変わります。
中古車を業務用で使う場合は、「事業用に使用しはじめた以降の使用可能期間の見積年数」が耐用年数です。
中古車の耐用年数は「法定耐用年数をすべて経過した中古車」か「法定耐用年数が途中の中古車」で、耐用年数の計算方法が変わります。
<中古車の耐用年数の計算方法>
|
①法定耐用年数をすべて経過した中古車 法定耐用年数の20%の年数 ②法定耐用年数が途中の中古車 (「法定耐用年数」-「経過した年数」)+(「経過した年数」×20%) |
※計算結果が2年に満たない場合は、2年が耐用年数
たとえば一般事業者が、5年落ちの軽自動車(法定耐用年数4年)を購入した場合の耐用年数は以下の通りです。
4年(一般用の軽自動車)×20%=0.8
2年を満たないので、この場合の見積耐用年数は2年です。
このように中古車の場合は、新車とは違う計算式で耐用年数を求めます。中古車は、何年落ちでも最低2年は償却可能です。
中古車でも新車の耐用年数が適用されることも
中古車に支払った費用がその車の取得価額の50%を超えたときは、見積耐用年数は使われません。この場合は、新車の耐用年数を適用します。
たとえば、普通車100万円(新車価格)の中古車を80万円で購入し、その車を60万円で改造するとしましょう。この場合、中古車に支払った費用が50万円(新車価格の50%)を超えていますので、新車の耐用年数6年が適用されます。
中古車を早い期間で償却したいときは、中古車にかける費用は取得価額の50%までにしましょう。
どうやって車の減価償却費を計算する?
車の減価償却費を計算するにあたって用いるのは、主に「定額法」と「定率法」の2つです。
定額法と定率法のそれぞれで車を減価償却する場合の、減価償却費の計算方法について見ていきましょう。
車の取得価額を計算する
定額法・定率法に関わらず、車の減価償却費を計算するためには、まず車の取得価額を計算します。
車の取得価額とは、車の購入代金や、事業用に使用するために支払った費用の合計額です。車の取得価額には、「取得価額に含める費用」と「取得価額に含めない費用」、「取得価額に含めても、含めなくてもよい費用」の3つに分けられます。
<車の取得価額に関する費用>
|
取得価額に含める費用 |
車両本体価格 |
|
車の付属品(カーナビ、ドライブレコーダーなど) |
|
|
納車費用 |
|
|
取得価額に含めない費用 |
自動車重量税 |
|
自動車税 |
|
|
自賠責保険料 |
|
|
取得価額に含めても、含めなくてもよい費用 |
自動車取得税 |
|
申請代行費用(名義登録や車庫証明など) |
車両本体やその付属品、納車費用は車の取得のために支払っているので、車の取得価額に含めます。一方で自賠責保険料は、運行による損害補償のための保険なので、車の取得に必要な費用ではありません。そのため自賠責保険料は、取得価額に含めず経費に計上します。
どちらにも該当しない費用は、減価償却費か経費計上のどちらかを選びます。
(定額法)取得価額に定額法の償却率をかける
定額法とは、取得価額に定額法の償却率をかけた額で減価償却する方法です。定額法の特徴は、毎年一定額を減価償却費に計上できることです。
減価償却費=車の取得価額×償却率(定額法)
定額法の減価償却費は、取得価額に定額法の償却率をかけて求めます。定額法の償却率は、耐用年数によって変わります。
<定額法の償却率(平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産)>
|
耐用年数 |
償却率 |
|
2年 |
0.500 |
|
3年 |
0.334 |
|
4年 |
0.250 |
|
5年 |
0.200 |
|
6年 |
0.167 |
※ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第八より作成
たとえば、耐用年数6年、普通車を100万円で取得したときの減価償却費は以下のようになります。
<耐用年数6年の普通車を100万円で取得したときの減価償却費(定額法)>
耐用年数6年の償却率:0.167
減価償却費:1,000,000円×0.167=167,000円(最終年度は期末に1円残すため164,999円)
|
年度 |
減価償却費 |
期末帳簿価額 |
|
1年目 |
167,000円 |
833,000円 |
|
2年目 |
666,000円 |
|
|
3年目 |
499,000円 |
|
|
4年目 |
332,000円 |
|
|
5年目 |
165,000円 |
|
|
6年目 |
164,999円 |
1円 |
このように定額法では、毎年一定の額で減価償却費を計上することになります。
(定率法)未償却残高に定率法の償却率をかける
定率法とは、未償却残高に定率法の償却率をかけて減価償却費を求める計算のことです。定率法の特徴は、はじめの年は減価償却費が高くなり、年が経過するにつれて少なくなっていきます。
減価償却費=未償却残高×償却率(定率法)
また、定率法では「償却保証額」を設けており、減価償却費が償却保証額に満たなくなった(減価償却費<償却保証額)年以降は、減価償却費は以下のようになります。
減価償却費=改定取得価額×改定償却率
(償却保証額=取得価額×保証率)
※改定取得価額…減価償却費が償却保証額を下回った最初の事業年度の期首帳簿価額
<定率法の償却率(平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産)>
|
耐用年数 |
償却率 |
改定償却率 |
保証率 |
|
2年 |
1.000 |
- |
- |
|
3年 |
0.667 |
1.000 |
0.11089 |
|
4年 |
0.500 |
1.000 |
0.12499 |
|
5年 |
0.400 |
0.500 |
0.10800 |
|
6年 |
0.333 |
0.334 |
0.09911 |
※ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第十より作成
さきほどの定額法の例と同様に、耐用年数6年、普通車を100万円で取得したときの減価償却費を定率法で求めると以下のようになります。
<耐用年数6年の普通車を100万円で取得したときの減価償却費(定率法)>
耐用年数6年の償却率:0.333%
償却保証額:10,000,000円×0.09911=99,110円
|
年度 |
減価償却費 |
期末帳簿価額 |
|
1年目 |
333,000円 |
667,000円 |
|
2年目 |
222,111円 |
444,889円 |
|
3年目 |
148,149円 |
296,740円 |
|
4年目 |
99,111円 ※償却保証額を下回るので、改定償却率を適用 |
197,629円 |
|
5年目 |
99,111円 ※改定償却率を適用 |
98,518円 |
|
6年目 |
98,517円 |
1円 |
※端数は切り上げ
このように定率法では、初年度の減価償却費は高くなり、年が経過するにつれて減価償却費が少なくなっています。
定額法と定率法はどっちが良い?
定額法か定率法のどっちが良いかは、「なるべく利益を残す」か「費用を早めに計上する」かで変わってきます。
定額法だと毎年同じ額の減価償却費を計上するので、償却している期間に多く利益を残すことが可能です。
一方で定率法だと、はじめの年ほど減価償却費を多く計上するので、早い時期に費用を計上できます。利益に余裕がある事業年度では、定率法の方がよいでしょう。
このように定額法か定率法のどちらがよいかは、費用をどのように計上したいかによって異なります。
中小企業なら30万円未満の車を一括で償却できる!
中小企業の場合、「少額減価償却資産」によって、30万円未満の車を一括で償却できます。
中小企業が30万円未満の安価な車を購入したとき、その車を購入した年度に、取得価額を一括で償却できます。
ここでの中小企業の定義は、以下の通りです。
<中小企業の定義>
|
・青色申告しており、資本金が1億円以下 ・常時雇用する従業員が1,000名以下 ・事業年度開始日以前の各事業年度の所得平均額が15億円以下 など |
少額減価償却資産を利用すると購入年度に一括で償却できるので、早めに経費計上して税金を抑えたい中小企業におすすめです。
車を減価償却するときの注意点
車を減価償却資産にすることで、償却期間中は減価償却費で経費にできます。一方で車を減価償却するときは、注意点があります。
維持費がかかる
車を減価償却するときには購入費用ばかりに目が行きがちです。しかし、車を保有している間には維持費がかかります。
<車の維持費一例>
|
・自動車税や自動車重量税などの税金 ・自賠責保険や任意保険などの保険料 ・車検やタイヤ交換などのメンテナンス費用 ・ガソリン代 など |
車の維持費だけで1台あたり年間50万円以上することもあり、無視できる費用ではありません。業務用で車を購入するときは、維持費も考慮した資金計画が必要です。
節税目的で車を買わない
業務に必要な場合に車を買うのはよいですが、節税目的で買うのはおすすめしません。
節税目的で買ったような車は、購入した年に全額経費にできないことがほとんどです。車には耐用年数があり、その期間で償却していきます。たとえば耐用年数6年の新車を買うと、車の取得価額を6年かけて償却していくことになります。つまり、節税目的で買ったからといって、購入した年に全額経費にできるわけではありません。
先ほども述べたように、車を購入すれば維持費もかかります。無理にいらない車を買って税金対策をするぐらいなら、おとなしく税金を支払う方がよいでしょう。
車は減価償却できます
車は減価償却で節税できることを解説しました。
新車の場合、耐用年数は普通車が6年で、軽自動車が4年です。車を減価償却するときは、毎年一定の金額で償却する「定額法」と、はじめの年は減価償却費が高くのちに少なくなる「定率法」の2つあります。どちらの計算方法で減価償却するかは、税理士などに相談するのがおすすめです。
ただし、節税目的で車を買うのはおすすめしません。維持費や償却期間を考慮した資金繰り計画で、本当に車が必要か考えてから購入するようにしましょう。
この記事が気に入ったらいいね!しよう
マネストの最新エントリーが見られます。
Twitterでマネストをフォローしよう! @ManeSto_comさんをフォロー